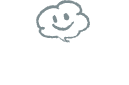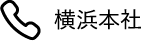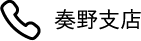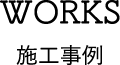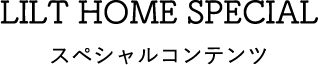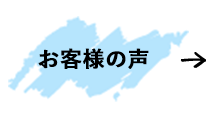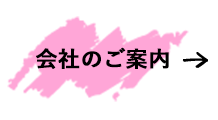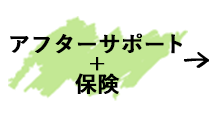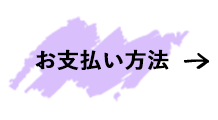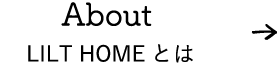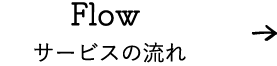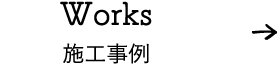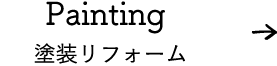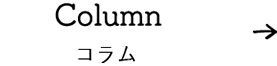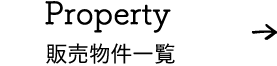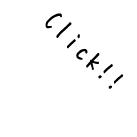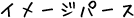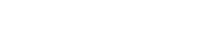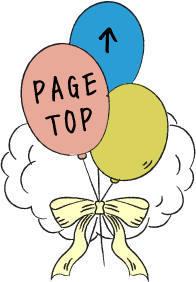縁のないすっきりとした見た目の半帖畳は、おしゃれで洗練された雰囲気の和室を作ることができる人気のアイテムです。目の向きと光の反射で浮かび上がるきれいな市松模様は、純和風の一般的な畳よりも、空間に違和感なく馴染みます。
今回は和モダンな和室を作る上で人気の「縁無畳」と「琉球畳」に焦点を当て、それぞれの違いや特徴を紹介したいと思います![]()

縁無畳と琉球畳の違い
縁無畳と琉球畳の違い?縁のない半帖サイズの畳のことを琉球畳と言うんじゃないの![]()
![]()
と思われている方も多いかもしれません。実際自分もそうでした![]() が、実は違うのです。
が、実は違うのです。
縁無畳と琉球畳は畳表(畳の表面)にあたる部分の素材が全くの別物で出来ています。
![]() 縁無畳・・イ草や新素材(樹脂・和紙表)などの素材を使って、畳縁を縫い付けずに作った畳のことを言います。一般的な長方形の畳と同じ素材です。
縁無畳・・イ草や新素材(樹脂・和紙表)などの素材を使って、畳縁を縫い付けずに作った畳のことを言います。一般的な長方形の畳と同じ素材です。
![]() 琉球畳・・カヤツリグサ科の七島イ(しちとうい)という植物を使った畳のことを言います。沖縄でよく栽培されていたので、そこから名前をとって琉球畳と呼ばれていました。
琉球畳・・カヤツリグサ科の七島イ(しちとうい)という植物を使った畳のことを言います。沖縄でよく栽培されていたので、そこから名前をとって琉球畳と呼ばれていました。
サイズや縁の有り無しに関わらず、七島イを使用した畳が琉球畳なのです![]()
一般的な畳と琉球畳は素材が違うんですね。そうなると畳を交換したりするときに、どちらを選ぶのが良いのでしょう。
ここからは、それぞれの畳の特徴を上げていきたいと思います。
■質感
普通の畳は使い始めからつるつるとした質感ですが、琉球畳はザラザラとした素材感のある手触りをしています。
イ草の断面の丸い形に比べ、琉球畳の七島いは断面が三角形になっているためです。
琉球畳は、使い始めの感触はケバが多く、ざらざらとした感触があり、数年かけて使い込むほどに柔らかくなっていくのが特徴です。この変化を楽しめるのも、琉球畳の人気の理由です。
■価格帯
琉球畳を敷きこむ場合、価格は一般的な畳の約2倍(時価)と言われています。
七島イの国産は大分県国東市で少数しか作られていません。さらに、七島イの生産・刈り取りなど製造過程のほとんどが手作業。織り上げるのにも通常の畳表より何倍もの時間がかかります。そのため納期も3ヵ月から6ヵ月かかることも。
農家さんの高齢化や生産者の数と生産量が減っていることから今後、琉球畳は希少価値の高いものとして、さらに価格が上昇していくと考えられます。
■耐久性
通常のイ草の縁無畳は、縁がない分、角が割れやすくなることがあります。また、畳表の織り方によっても耐久性が若干変わります。しかし、表替え・裏替えしが出来るため定期的にリフレッシュすることが可能です。
一方、七島イは強度がありながら、折って加工しやすいという特徴があるため、畳縁のない畳の原料として昔から重宝されてきました。
摩擦に強く耐久性に優れており、通常のイ草より約2倍の不燃性と3〜4倍の耐久性があるといわれています。一昔前には柔道場に使用されていました。
しかし耐久性があるものの、裏返しできない欠点があります。琉球畳に使用されている七島イは、固く柔軟性に乏しいため、無理に裏返しを行うと割れてしまう可能性があるのです。
琉球畳は素材がしっかりしているので、一般的な畳より長持ちしますが、使い心地や見た目が気になり始めたら新調しなければなりません。
畳選び、どちらを選ぶ?
イ草や新素材(樹脂・和紙)で作られた縁無畳はカラーバリエーションが豊富なので、自分の好きなテイストでコーディネートすることが可能です。(別のcolumnで紹介したセキスイ畳/MIGUSAの記事もご覧ください)
伝統色からモダン色、パステルカラーまで、豊かな色彩でオリジナリティあふれる和室を作ることができます。
見た目やデザインを重視する場合は、色々なカラーバリエーションが選べる縁無畳がおすすめです![]()

一方、国産七島イは、価格が高いですが耐久性が抜群。長く使う事ですばらしい風格と艶がでてきます。
和室をメインの生活空間として使うのであれば、耐久性を重視した選択が求められます。
上記のような畳の特性を考慮した上で、ライフスタイルや家のデザイン、予算に合わせて畳を選んでみてくださいね![]()
縁無畳を採用した施工例はこちら![]()


 045-947-3552
045-947-3552 お問い合わせ
お問い合わせ お客様の声
お客様の声